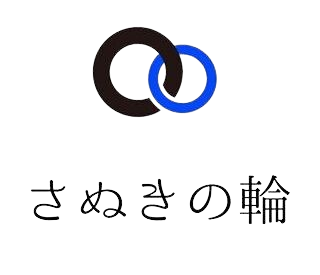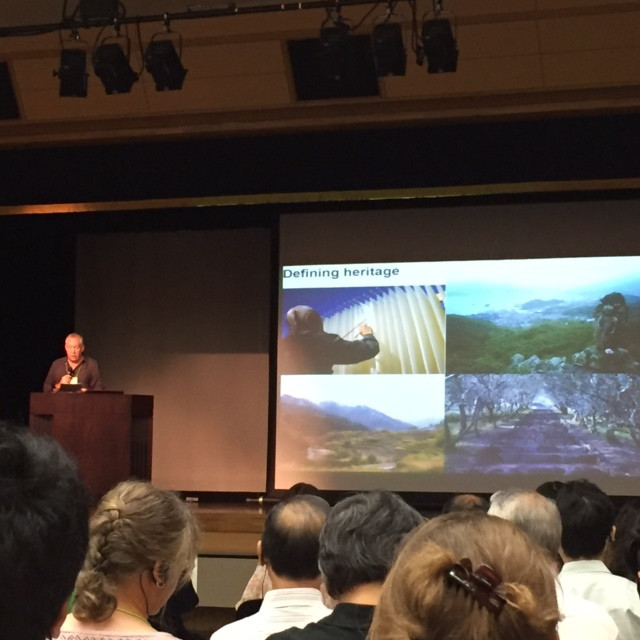WAC世界考古学会議の小豆島プレツアーが無事終わりました![]()
考古学の先生達は何に対しても興味津々で、どこに行っても何をしても、質問が止まることはありません![]()
「これは何?」「何のためにこうしてるの?」「これが使われ始めたのはいつ?」
「昔はどうやって運んでたの?」「それを証明したのは何?」「***年以上前に人がここに入ってなかったという証拠は?」 etc etc...
高度な質問にとまどう事もありましたが、ここまで興味を持ってくれると勉強した甲斐があります![]()
![]()
なかなか暑い日で、移動や天狗岩でのハイキングでみなさん疲れている様子だったので、豆腐岩丁場では「疲れている方はバスで待っててもらっても大丈夫ですよ」と案内しましたが、「暑いから上りたくないけど、面白そうなものがあるんだから、絶対行く![]()
![]() 」とほぼ全員が登り、やっぱりみなさん興味津々でした
」とほぼ全員が登り、やっぱりみなさん興味津々でした![]()
石ツアーのクライマックスでは、実際に石工の道具を鍛冶で作り、大きな岩を割りました![]()
![]()
昔の石工の方法で矢穴を掘ろうとしてます![]()
私も試しましたが、簡単に掘れるものじゃありません![]()
最後はプロの石工さんにお任せして、矢穴に矢を入れて、玄翁(げんのう)というハンマーで矢を叩きます![]()
何度も打ち付けた後、ヒビが入り始めると石からミシミシミシと割れる音が聞こえ始めます![]()
石工さん達は「石が鳴く」と表現されてました![]()
この音が聞えたら、割れるのはもうすぐっ![]()
![]() パカッ
パカッ![]() というより、
というより、![]()
![]() ミシミシッ ドーンッ
ミシミシッ ドーンッ![]()
![]() かな
かな![]()
割れた時、横にはひっくり返らずその場で割れましたが、それでもかなりの迫力です![]()
石目という目に見えないクラックの関係で右に線が逸れたようです。
これを石工さん達の間では、「逃げた」と言うそうです![]()
次に、現在でも実際に使用している近代的な方法で石を割ります![]()
矢穴も昔のように手作業ではなく、機械を使用して穴を開けます![]()
こちらは、なんと3たたき程度で。。。
![]()
![]()
![]() パァーンッ
パァーンッ![]()
![]()
![]()
と、勢いよく、まっすぐ2つに割れました![]()
![]()
こちらも石目の関係ですぐにまっすぐ綺麗に割れたそうです![]()
叩いて割っただけとは思えないくらい、まっすぐ割れてますね![]()
*水で濡れているのは、前の日の雨が穴に溜まっていただけです![]()
2日間のツアーの後はサンオリーブでシンポジウムを行い、小豆島の魅力やそれをどう次世代に残していくか等をみんなで討論されました。
先生達は小豆島の自然や温かい人にものすごく感動され、コメント中に感極まる方もいた程です!!!
ディスカッションで出たコメントをいつくかご紹介します。
「とてもスピリチュアルな島だ。小豆島の自然と人達の生活は絶対に守らなければならない。私の国では、間違った観光により良い環境が破壊された。小豆島には絶対にそうなって欲しくない。」
「小豆島の石も大変興味深かったが、ツアーの中で面白い鳥をたくさん見た。バードウォッチングを観光に取り入れてみては?」
「小豆島はこんなに魅力的な島なのに、このプレツアーに参加するまでは名前すら知らなかった。参加者約70人のうち、元々知っていた人はたったの2人であった。世界に魅力を伝えるために、もっと情報発信に力を入れてみては?」
---------------------------------------------------------------------
もう1つ、個人的に驚いたのは、ツアー中の地域のみなさんの協力です。
2泊3日のツアー中の食事はほとんど各地域のボランティアの方達が地元の食材を中心に使って作って下さってました![]()
![]()
![]()
![]()
ツアー関係者を含めると約100名分の食事を、朝早い時には夜中3時から集まって作って下さったそうです![]()
地域の繋がりがかなり強いところでないと、なかなか実現しないことだなぁと思いました![]()