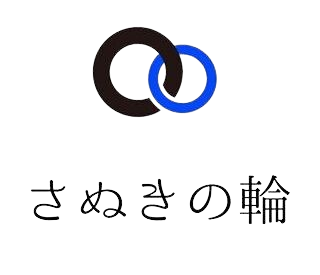今回は令和7年9月に任期満了を迎える土庄町の地域おこし協力隊、佐藤珠江さんにインタビューを行い、理学療法士から協力隊へ転身した経緯や活動内容、そして「"誰かの目"を気にする自分」から脱却し、町の未来を見据えて働くようになった現在と今後の展望について、お話を伺いました。
―本日は宜しくお願いします。まずは協力隊になる前についてお聞きしたいと思います。以前はどのようなお仕事をされていたのでしょうか。
大学卒業後、地元の栃木県や東京の病院で理学療法士として働いていました。
―佐藤さんのプロフィールで驚きだったのが、ダーツで旅行先を決めて、それが小豆島だったという。
そうです。実際にダーツの矢が刺さったのは海だったんですが、地図で測って一番近かったのが小豆島でした。
最初の滞在は4日間でしたが、その後は瀬戸内国際芸術祭(以下:瀬戸芸)の度に来ていました。
―移住前に何度も小豆島を訪れていたということですが、その時はいわゆる関係人口としての関わりだったと思います。そこから実際に移住を決断する転機のようなことはあったのでしょうか。
元々協力隊になりたいという思いがありました。実は2020年に北海道の協力隊に応募していたのですが、ちょうどコロナが流行り始めた時期と重なったこともあって、一度移住を断念したんです。そのタイミングで仕事を辞めてしまったため、別の仕事に就きました。そこで2年間は働こうと決めていて、その2年後に東京で移住フェアがあって、瀬戸芸関連のイベントもあったんです。そのイベントでやっていたスタンプラリーのために土庄町のブースに立ち寄ったら今の協力隊の募集の話をしていて。実はその数日前にその募集のオンライン説明会に参加したばかりだったので、「これもご縁だな」と思って応募を決めました。
―それでは実際の活動について教えてください。ミッションは移住相談対応ということで、具体的にどういう形で相談が来るのでしょうか。
主にメールでの問い合わせです。その他、電話や旅行のついでに直接役場の窓口に来る方もいます。まれですが協力隊のInstagramにDMで相談が来ることもありますね。
―ケースバイケースだとは思いますが、移住相談対応ではどのような話をしますか。
土庄町の説明から始める場合もありますが、移住先を漠然と考えている方は小豆島全体の移住相談を受け付けているNPO法人トティエを紹介します。立場上どうしても土庄町への移住のお話しかできないので。移住相談される方には小豆島全体を視野に入れている場合がけっこう多くて、実際話を聞いてみると小豆島町の方がいいみたいな話が出てきてしまうケースもあります。なので、漠然と小豆島への移住を検討されている方は一度トティエで相談を受けてもらって、具体的に土庄町への移住を検討するようになってから改めて土庄町に話を振ってもらうという役割分担をしています。
―アテンドをしたりはするのでしょうか。
空き家バンクに登録されている空き家を見に行くアテンドはします。その途中、車で通りながら地域の説明をしたりします。
あと以前は小豆島町とトティエと合同で、空き家見学ツアーをやったりもしていました。
―活動の中での喜びや印象に残った出来事はありますか?
移住相談に対応した方が、無事に移住された後に会いに来てくれて、「佐藤さんがいたから移住できました」といった言葉をかけてくださることがけっこうあるので、そういう時が嬉しいですね。あと、理学療法士としての経験や海外で生活していた経験を活かした活動に感謝してもらえることもあります。移住する前は当たり前にしていた活動でも、喜んでもらえたりするので、そういうところも嬉しいことですね。
―「理学療法士や、海外での経験を活かした活動」というのはどういった活動でしょうか?
私のミッションは移住定住促進や空き家バンクなのですが、そこから派生して健康福祉課と連携し高齢者の介護予防事業にも取り組んできました。具体的には、フレイル予防教室に同行し、理学療法士の経験を活かして運動指導や健康講座をやったりしました。私は高齢者分野の専門家ではないですし、理学療法士としてすごいできるわけでもないですが、ちょっとした知識を伝えるだけで、「今日の話すごい良かったよ」と言ってくれたり、簡単な運動指導をすると、「毎日やってるよ」と会うたびに言ってくれたりするんです。こうした活動は、将来的に土庄町の介護費の軽減することにもつながるかもしれませんし、自分が町に貢献できていると感じられます。
また、小豆島町地域おこし協力隊OBの喰代さんが代表を務めている一般社団法人Lingoの活動も一緒にやらせてもらっていて、外国人住民の日本語教室や交流会もやっています。これは海外での経験が活きてますね。
―そういった活動は地域おこし協力隊のミッションとは別でされているんでしょうか?
そうですね。ただ完全に別ということでもなく、すべてが繋がっています。介護予防事業は、根底に「空き家の掘り起こし」という目的があります。私が地域に出て活動し顔を知ってもらうことで、「実はうち空き家あるんだよね」と気軽に相談してもらえる関係性が生まれます。実際にそこから空き家バンクへの登録に繋がったことがありました。担当者の顔が見えないと、電話や窓口での相談をためらってしまうかもしれません。なので、立ち話から始められるような、心理的なハードルの低い相談環境を作りたいと思っていました。
Lingoでの活動は、外国人住民の「定住促進」活動ですね。今まで移住定住関係のイベントは、どうしても日本人向けの情報発信になりがちで、日本人からしか参加の申し込みがありませんでしたが、今土庄町には約150人の外国人が暮らしていて、人口の1%くらいになります。彼らも移住者なのでサポートは必要だと思っていました。単身で来ていると職場の人としか関われなかったりするので、交流会を開くことで自分と同じような悩みを抱えている人たちと出会えたり、私たちが生活のことなどいろんな相談にのっていることを知ってもらえるだけで、ちょっとは楽になるんじゃないかなと思っています。
―これまでの話とは逆に、協力隊になる前にイメージしていた協力隊と実際のギャップや、活動の中で苦労したことはありますか?
大きく三つあったかなと思います。一つ目は、役場の方や地域の方がとても協力的で、そこはいい意味でのギャップでした。
二つ目は、町に課題はあるけど、どこか他人事のように感じられる場面があったことです。これは土庄町だけでなく、どこの町でもあることだと思いますが…。例えば空き家もたくさんあるのに「売りたくない」とか「貸したくない」とか。もちろん、いろんな事情はあると思います。私も同じ状況だったらそう考えるかもしれません。しかし、移住相談をたくさん受けていると、本当に島に来たいと思っている人たちの住む場所がなくて移住できないという現実を目の当たりにします。島の未来を考えると、少しもどかしい気持ちになることもありました。
三つめは協力隊の立場が思ったより難しいというところです。協力隊は地域と行政を繋ぐような役割があると思っているのですが、裏を返せばどちらの側でもないというか、どちらからしても「外の人」という見られ方をしていると感じることがたまにありました。地域の方からは「3年経ったらいなくなるんでしょ」というようなことを言われたこともあって、そういった点は苦労しました。
―そのような状況の中で意識されていたことはありますか?
(役場と地域)両方の意見を傾聴することです。あと提案が通らず停滞しているときは、無理やり進めるのではなく、焦らず一歩引いて、あえて何もせず、状況を俯瞰して見ることを意識していました。そうすると「ちゃんとこちらのことも考えてくれているな」とか「あの人は悪い人じゃないな」と思ってもらえたりするので。
―協力隊の活動を通して成長できたことはありますか?
自分軸で動けるようになったことだと思います。以前は人の評価を気にして自分の意見を言えないタイプだったんですけど、今は課題に向き合って、どのように動けば改善できるのかなど自分なりに判断して動けるようになったと思います。
あとは聴く力や待つ力が養われたと思います。
―協力隊としてのどのような活動がその成長に繋がったと思いますか?
移住相談の際に、島の不便な点やデメリットもしっかり伝えるようにしていることが大きいと思います。今までの自分だったら、角が立つことを恐れて、そういったことは言わずに受け入れていたと思います。ですがせっかく移住するなら長く住んでもらいたいですし、本当に地域のことを考えたらデメリットも含めて理解した方に移住・定住してもらうことが地域の課題解決につながるので、町のためにはどうしたらいいのかというのをすごく考えるようになりました。
あと、移住の仕事は成果がすぐに見えません。1年2年じっくりかけてやっていくものだったりします。以前の理学療法士の仕事は、治療によって患者さんがすぐに改善するなど、成果が目に見えやすいことがありました。そのため、この活動を始めた当初は成果がすぐに見えず、「自分のやっていることは本当に正しいのだろうか」と判断ができず戸惑ったこともありました。しかし今では「どうすれば、より良い結果につながるか」を長期的な視点で考えられるようになりました。
―お話を聞いていると活動を通して、今までの"人からどう見られるか"という価値観よりも"どうしたら町のためになるか"という価値観が上位に変わったように感じますが、その転換はどのように起こったのでしょうか?
私は体育会系の部活をしていた経験から、「上からの指示は絶対」という感覚が染みついていました。常に目上の人の評価を気にしていたため、「人からどう見られるか」を強く意識するようになっていたのだと思います。一方、今は協力隊という立場で、直属の上司がいない環境なので、個人として主体的に活動ができています。もちろん役場の担当職員さんや、一緒に活動する仲間・地域の方々など、見てくれている人はいます。そういう方々と上下関係ではなく「フラットな立場」で協力し合える。この関係性で仕事ができるということが、私にとってとても大きいかなと思います。
また、協力隊として活動するようになってから、本当にいろんな価値観の人たちと出会って、そういった人たちと一つの町でともに生きるという感覚も養われてきたと思います。
あと、私は協力隊でもありながら、フリーランスとして副業をやっているのですが、それも大きいと思います。雇われている立場ではないので自分で判断しなければいけない状況も多く、全部自分ごととして考えなければいけないということが身に染みてわかりました。
―移住してから感じた土庄町の良いところを教えてください。
香川県全体でアピールしていることでもありますが、ほどよく都会でほどよく田舎なところだと思います。土庄町ってすごく便利なんです。もちろん場所によっては不便なところもありますが、町の中心部は何でもあるし、海が見たいなと思ったらすぐ見に行くことができます。高松に行くときもフェリーですぐに行けるのもいいところです。
あと、私は地元も好きなので休みの日に帰ったりするのですが、その際もアクセスがいいと思います。飛行機でも帰れますし、土庄から岡山までのフェリーもあるのでそこから新幹線でも行けるので。飛行機だとある程度前もってチケットを取っておかないといけないですが、新幹線であれば直前で大丈夫なので、そういった意味でも新幹線へのアクセスが比較的いいこともポイントだと思います。
その他の面でいうと、土庄町は移住者も多いので、移住者慣れしているというのもいいところです。土庄町を選んでくれてありがとうという雰囲気もあります。私としては好きで来ているんですけど、それでも感謝されたりします。あと都会にいると、私は大勢いる "理学療法士の一人" にすぎませんでした。理学療法士の資格を持っていたとしても、そういう人がたくさんいるので、自分があまり活きないんです。でも土庄町ではそういったことが希少だったりして、先ほどもお話したように、今まで普通にやっていたことでもすごく感謝されたりするので、そういったところはすごくありがたいなと思います。
―先ほどのお答えと相反することもしれませんが、ちょっと高松に出るとなってもフェリーに乗ることになるので、車を持っていこうと思うとけっこうな費用が掛かると思います。普段はいいかもしれないですが、旅行する際などの不便さといった点はどうでしょうか?
それはすごくあります。それこそ旅行の時もそうですが、重病になった際などは島内の病院で対応できないこともあるので、そういった時は困るなというのはあります。
なので移住相談の際にもそういったことはお伝えするようにしています。


佐藤隊員お気に入りの「屋形崎夕陽の丘」。夕方にはきれいな夕日が見えるスポットです。
―9月の退任以降の予定はありますか?
はい。あります。6月1日に旧土庄高校の3階に「ユカリノSPACE小豆島」という町営の多目的交流スペースがオープンしたのですが、卒業後を見越して今はこちらの運営に携わっています。なので、引き続きここの運営に携わっていく予定です。

土庄町多目的交流施設「とのたる館」。この建物の3回が「ユカリノSPACE小豆島」です。

―「ユカリノSPACE小豆島」にはどのような経緯で関わることになったのでしょうか?
もともと旧土庄高校の活用として、サテライトオフィスやコワーキングスペース・サテライトキャンパスの開設という構想がありました。私は以前から個人で仕事をしていたので、コワーキングスペースをよく利用していたこともあり、コワーキングスペースの運営にも興味を持っていました。そんな話を域学連携の協力隊だった森さんとしていたら「よかったら一緒にやらない?」と誘ってくれたんです。そこから1年間くらい一緒に活動して、現在に至ります。
―今後の活動の展望はありますか?
勝手な構想ですが(笑)ゆくゆくは「ユカリノSPACE小豆島」を移住関係のハブのような場所にもしていきたいです。私がここにいたら移住の相談を受けることができますし、他の協力隊とも連携して、仕事の相談ができたり、下の階に学童保育や放課後子ども教室もあるので、子育ての相談もできるような場所にできたらと思っています。サテライトオフィスやサテライトキャンパスもあるので、学生と地域の方・移住検討者が交流できるような施設にもなるといいなと思っています。
―最後に協力隊に興味を持っている方へのアドバイスをお聞きしたいのですが、まずは協力隊を探す上でのアドバイスはありますか?
まず、少しでも土地勘があったり、その地域のことをちょっとでも知っている場所を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。知っている場所でも実際来てみるとギャップがあるので、知らない場所だとより大きなギャップを感じるかなと思います。募集内容については、性格にもよると思いますが、フリーミッションよりは、ある程度具体的なミッションがある方がやりやすいと思います。自分で起業してやっていきます!みたいな方だったら全然フリーミッションでもいいと思うんですけど、地域に馴染むという意味でも具体的なミッションがあった方が入りやすいかなと思います。あとはすでに協力隊がいる地域の方がいいかなと思います。土庄町は先輩や同期の隊員がたくさんいて相談しやすい環境です。私自身、今振り返るとそういった方々がいなかったら超えられなかった壁があったなと思うので、とても助かっています。もちろん近隣の市町村の協力隊と関われるような環境であればいいと思いますけど、孤立してしまうような環境だと大変かなと思います。
―次は協力隊として活動する上でのアドバイスはありますか?
協力隊になるからにはやりたいことがあると思うんですけど、自分の意見を押し通すのではなくて、まずは人の話を聞く。当たり前のことかもしれないですが、人の話を聞いて信頼貯金をためていくことがすごく大事なことだと思います。あんまり最初からスピードを出して活動していくというよりは地固めをしっかりする方がいいのかなと思います。
あと、質問の意図とずれるかもしれないですが、いろいろな経験を積んで「引き出し」を多く持っておくといいと思います。旅行が好きとか、○○が得意とか、趣味みたいな感じで何でもいいと思いますが、そういったところから話が弾んで地域に馴染んで行けたりするので。私自身飽きっぽい性格もあって、短期的なアルバイトなどいろんな経験をしてきました。今までは遠回りしたと思っていましたが、そういった経験が今に生きていることがたくさんあるので、大事な経験だったと今は思っています。

(土庄町でともに移住定住促進に取り組む堀川隊員(左)、小林隊員(中央)と。相談しあえる仲間が多くいることも土庄町地域おこし協力隊の魅力です。)